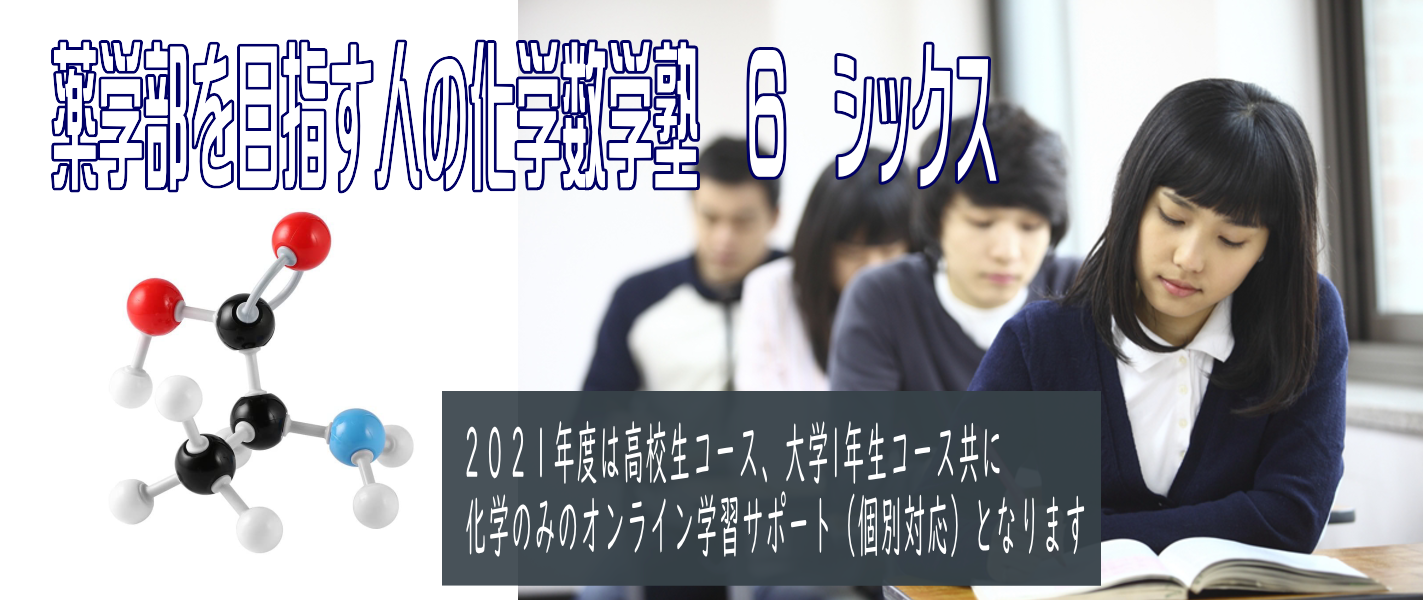薬学部を目指す人の化学数学塾 シックスは高校化学の基礎を最重要視しています
当塾は薬学部など理数受験科目が化学及び数Ⅰ/A/Ⅱ/Bの高校生の学習サポートを主としています。
塾名の”シックス”は有機化学の必須原子である炭素の原子番号6から名付けました。
私は現在私大薬学部に通う子供を持つ親であり、随分昔になりますが自身は英語・数Ⅱ・化学で私大獣医学科を受験し入学しました。
医学部を除いては化学、物理、生物から受験科目を選択できる場合が多いと思います。この3科目の中から私が敢えて化学を選択した理由。 その答はシンプルです。 ”勉強を教えてくれた方が化学が得意だったから” それだけです。
化学に興味を持った、化学に関係した仕事をしたかったからでも何でもありません。
そんな始まりでも先生の教え方が上手だったのか化学の成績は非常に良かったです。実際有名予備校の模試でも化学の偏差値は70以上ありました。
しかしこれは定番の解法パターンを暗記した結果に過ぎませんでした。どの科目にも当てはまりますが、実際は理屈が良く分かっていなくてもひたすら問題を解いて解法パターンを覚えて行けば自ずと成績は上がるのです。
大学に入っても先輩などから過去問を手に入れてこのやり方を行えば単位は落とさない・・・筈なのですが、先生が変われば突然出題傾向は変わります。
また昨年からのコロナの影響で大学ではオンライン授業が増えており、大学も先生達も手探りの状態です。その為先生は変わらないのに出題傾向が変わる事も珍しくありません。
更に学生同士の交流も制限され先輩から過去問を手に入れる事もなかなか難しい状況です。
何とか手に入れてあれだけ過去問を攻略したのに、実際の試験では全く予想が当たらず慌てた学生さんも少なくないのではないでしょうか。
解法パターンをひたすら暗記する学習はこの様に大きなリスクを持っています。
どんな問題が出ようと対応できる様にするには、やはり日頃の学習しかありません。
ところが大学に入ると哲学書か?と思う様な説明が殆ど無い教科書を使用する事がざらにあり(特に先生自身が著者であるケースはもれなくこれが当てはまります)、勉強したくても何が何だかさっぱり分からないという事は珍しくありません。
それでは良く分からない学科は参考書でも買って・・・と考えるでしょうが、高校生まではあれ程沢山の参考書が発売されていたのに、大学生向けとなると極端に減り、特に理系科目の場合はあってもかなり高額な代物になる事が多いです。
しかし現在はインターネットという物凄く便利なツールがあります。
そこには教科書や参考書や問題集とは比べ物にならない程膨大な情報が存在し、高校生も含めて学習サポートには最強のアイテムだと思います。
知りたい事を詳しく説明してくれているサイトも沢山ありますし、質問をすれば答を教えてくれる人までいます。
しかし誰もがその恩恵にあずかれる訳ではありません。
必要な情報を手に入れる為には「的確な検索ワード」と「その情報の真偽を見極める力」を持っていなければならないのです。
自分が思いついた検索ワードではヒットしなかったり絞り込めない場合は更に的確なワードを思いつかなければなりませんし、〇〇知恵袋的なサイトを覗くと明らかに間違っている回答に質問者がお礼を言っている事は珍しくありません。
「何て調べて良いかすら分からない・・・」、「検索したけど欲しい情報まで辿り着けない・・・」、「念の為別のサイトを見たら内容が異なっていて、どちらが正しいか分からない・・・」という有様では宝の持ち腐れなのです。
当塾は化学の学習をサポートする塾なので化学についてお話しすると、私が大学に入って感じたのはあれ程成績が良かった筈なのに実は全く基礎が分かっていないという事でした。
例えば「酸や塩基とはどの様なものですか?」という事は高校化学で学習しますが、もう一歩進んで「共役酸や共役塩基とはどの様なものですか?」までは良く分かっていなくても学校の問題は解けてしまいます。
しかし大学で使う教科書はすごく丁寧に説明してくれている本でも、わざわざ高校までに習って来た筈の基礎については解説は書いてありません。
「強塩基の共役酸は弱酸である」と当たり前の様に書いてあります。
そこでネットで「共役酸」と検索してみます。
すると山の様にサイトがヒットします。しかしその内容が理解できるか、その情報の真偽の判断はある程度の基礎知識が必要です。
逆に言えば、基礎知識をきちんと習得しておけば、様々なツールを有益に使用できるという事です。
確かに志望大学に合格してこその話ですが、試験科目の解法パターンを単に暗記しただけでは大学入学後に大いに戸惑う事になります。
薬学部では毎年200人中40人が留年するなんて大学も決して稀な事ではありません。
何遍も繰り返しますが重要なのは”基礎”の習得です。
私はわが子に勉強を教える過程で数学や化学を再び学習する事になりました。
他人に教える為には自身が理屈を分かっていなければならないので、結果として化学の基礎をきちんと学び直す事ができました。
生徒の皆さんには、この様に基礎をしっかりと身に着けていただく事で応用力も発揮できる様になっていただきたいと思っております